農学生命科学部・本多和茂准教授、被ばく医療総合研究所・三浦富智教授、弘前公園で長年桜守を務めた樹木医の小林勝さんは、浪江町の桜復興ボランティアグループ「絆さくらの会」と協同で、令和7年9月4~5日に浪江町リバーラインの桜の芽接ぎを行いました。本事業は福島イノベーション・コースト構想推進機構「大学等の『復興知』を活用した人材育成基盤構築事業」における桜復興・観光資源保全に向けた教育プログラムの一環として実施しています。
今回、浪江町住民がリバーラインのソメイヨシノの中で早咲きの変異枝(枝変わり)があることを見つけたことがきっかけとなり、弘前大学は、絆さくらの会の依頼を受け、芽接ぎという方法でこの早咲き変異枝を増やすことに挑戦しました。
リバーラインのソメイヨシノ変異枝から葉芽のある枝を採取し、台木となるオオシマザクラの苗木に移植する方法です。
前日に採取した変異枝から葉芽を探し、小林樹木医と本多先生の指導を受けながら芽接ぎを行いました。作業には、フランスからの留学生であるジャンヌ・ブイエさんらも参加し、浪江町の桜を復興させるプログラムを見学・体験しました。
数年後、リバーラインで見つかったソメイヨシノ早咲き変異枝が浪江住民に親しんでいただけることを願っています。
浪江町で桜復興プログラム リバーラインの桜の芽接ぎ
 新着情報
新着情報11:住み続けられるまちづくりを
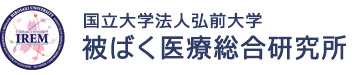



1-300x225.jpg)
-1-300x178.jpg)

