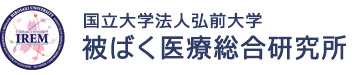福島原発事故から14年が経ちましたが、今でも福島県内では復興のための活動が盛んに行われております。弘前大学は2011年より浪江町を中心としてさまざまな支援活動を継続しています。これらの活動の一環として、2017年度から環境省の委託を受けて浜通り地域での環境放射能調査を実施しております。2021年からの3年間は、長崎大学と連携して川内村、富岡町、大熊町でも環境放射能調査を実施しました。その成果の一部として、飲料水中のラドン、トリチウム、セシウム137の放射能濃度を評価し、天然放射性核種であるラドンの被ばく線量とトリチウムやセシウム137からの被ばく線量の対比を行いました。この成果は米国化学協会から出版されているEnvironmental Science and Technology(インパクトファクター: 10.9)に掲載されました。
放射線被ばくに対する不安や誤解が多い中、自然界に元来存在している放射性核種からの被ばく線量を“ものさし”として福島原発事故由来の放射性核種による被ばく線量を住民自身が比較できるデータセットを揃えることは放射線リスクコミュニケーションにおいて非常に意義があることだと考えております。
なお、被ばく医療総合研究所では、環境省の委託を受けて2024年度からこの活動を福島県全域に展開しております。
Donovan Anderson, Yuki Oda, Yasuyuki Taira, Yasutaka Omori, Hirofumi Tazoe, Naofumi Akata, Chutima Kranrod, Ryohei Yamada, Haruka Kuwata, Yuki Tamakuma, Hiromi Kudo, Minoru Osanai, Natsuki Nishimura, Yumi Yasuoka, Tetsuya Sanada, Masahiro Hosoda, Shinji Tokonami. Fukushima’s Tap and Groundwater a Decade after the Nuclear Accident with Radiocesium, Tritium, and Radon, Environmental Science & Technology, 59:4906-14 (2025)
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.4c14601