2025年2月17日及び18日に床次眞司所長(計測技術・物理線量評価部門教授)と細田正洋教授(国際連携・共同研究推進部門兼任)は、アデレード大学及び世界最大の鉱業会社であるBHPを訪問しました。
アデレード大学では、Centre for Radiation Research, Education and InnovationのTony Hookerセンター長を訪問し、職業被ばくや公衆被ばくに対する研究や教育を共同で実施していくための基本合意書の締結に向けた打ち合わせを行いました。また、同センターの研究室を視察や、ラドン曝露場での動物実験の様子なども見学し、安定したラドン子孫核種の曝露技術の確立に向けた協力が期待されます。また、同センターとオーストラリア放射線防護学会南オーストラリア支部の共同セミナーで被ばく医療総合研究所での研究について講演を行いました。Hookerセンター長とは、これまでIAEAのプロジェクトでの協働や、国際放射線防護セミナーでの講演等を通じて交流を続けてきました。今後は基本合意書の締結に向けてより密度の濃い交流を継続する計画です。
18日には、床次所長が会長を務めるアジア・オセアニア地域ラドン協会(AORA)の副会長であるJim Hondros氏からの相談を受けBHP(アデレード支社)を訪問しました。BHPは南オーストラリア州にある世界最大のウラン埋蔵量を誇るオリンピックダム鉱山で銅やウランの採掘を行っています。この採掘に伴い大きな問題となるのがラドンによる作業者の被ばく管理ですが、現状ではカナダにある企業に支援を委託するしかない状況であることが今回の訪問で分かりました。さらに、レアメタルの採掘ではトロンの被ばくが問題となりますが、この問題に対応できる機関が存在しないとの懸念が強調されていました。
欧州ではフランスを中心として資源開発に伴う被ばく管理に関する研究や技術開発が行われてきています。しかし、最近では研究機関や企業の組織改編などにより、鉱山開発に伴うラドン(もしくはトロン)の被ばく対策に関する国際協力が十分行き届かない可能性が出てきています。このように世界が抱える課題の中で、長年にわたり世界に類をみない独自の高度な技術によってラドンさらにはトロンによる被ばく線量を評価し、そしてその低減手法に関して多くの実績を積み上げてきた弘前大学に大きく期待が寄せられています。
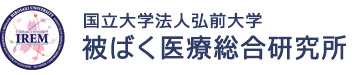

_resize.jpg)
_resize-300x225.jpg)
